「中小企業診断士」資格をとれば、コンサル転職に有利なのか
結論:「プラス材料」にはなり得ますが、それだけで合格を約束するわけではありません。
※あくまで個人の経験踏まえた見解である点ご容赦ください※
診断士の知識自体は上流(戦略立案など)で役に立ちますし、中小〜中規模ファームでは重宝される可能性が比較的高く、保有者がやや多い印象のため受け入れられやすい傾向があります。
ただし、最終的な判断は実務で何ができるかにかかっています。現場での課題解決やプロジェクト/企画の実績、志望動機の説得力、そして(特に戦略系に限っては)フェルミ推定やケース面接での対応力があげられます。
端的に言うと、診断士は「使い方次第で強い武器」になりますが、「これさえ持っていれば合格」という切り札にはなりません。これは特にBig4やアクセンチュアのような大手ファームで顕著な印象があります。
大手ファームの場合
大手ファームの場合では特に、資格以上に以下のポイントが重視されている印象です。
現場経験:課題発見から解決までの実績や、プロジェクト/企画を自分で回した経験が最も重視されます。
志望動機:なぜそのファームで何をしたいのか、筋道が通っているかをきちんと説明できることが重要です。
ケース面接・フェルミ推定の出来:戦略系のポジションでは必須(他(総合系、IT系等)は課されない場合も多い)です。短時間で妥当な仮説を立て、論理的に説明する力が合否を左右しやすいです。
- フェルミ推定:限られた情報で概算を出す練習です。問題を分解して妥当なレンジを示す力が求められます。
- ケース面接:提示されたビジネス課題に対して、仮説→検証→提案を短時間で組み立てて伝える形式です。どの切り口で問題を分けるか、結論と根拠をどう示すかが見られます。
どちらも「資格の有無」より「その場でどれだけ論理的に動けるか」を測る場です。
(上記に関しては今後、対策含めて詳しく解説していきたいと薄っすらと思っております)
診断士で得られる経営や事業分析の知識は、特に上流工程(戦略立案や事業戦略の設計、事業計画のロジック構築など)で役に立ちます。ただし、知識があるだけでなく、それを実務の中でどう使ったか(インサイトを導いた経験)を語れることが評価につながります。
中堅~中小ファームの場合
ここでは診断士の認知度が相対的に高く、周囲に保有者がやや多い場合にはがあるため受け入れられやすい傾向があります。クライアント側が診断士を持っているケースは少ないことが多いものの、採用側や同業者の間で評価されやすい点は事実です。ただし、「資格がある=絶対有利」ではなく、やはり現場で何ができるか、どれだけ成果を出せるかが最終評価になります。
- 実績の言語化:自分の経験を「背景→自分の役割→施策→定量的な結果」で短くまとめましょう。面接や職務経歴書で伝わりやすくなります。
- 志望動機の整理:なぜそのファームで何をしたいのか、具体的に言えるようにしておきましょう。
- 知識の実務化:診断士で学んだフレームや分析を、実際の案件でどう応用したかを示せると効果的です。
- フェルミ推定・ケース面接の訓練:戦略系を狙うなら必須です(他は課されない場合もあります)。短時間での論理構築力を磨いておくと安心です。
最後に
中小企業診断士は、状況によってはとても有効な武器になります。大手を狙うなら資格はプラス材料として活かしつつ、まずは現場実績の整理とケース力の強化を優先してください。中小〜中規模ファームでは相対的に認知度の面で受け入れられやすい場面がありますが、最終的な評価はやはり「現場での貢献」が基準になります。

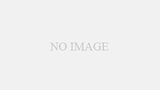
コメント